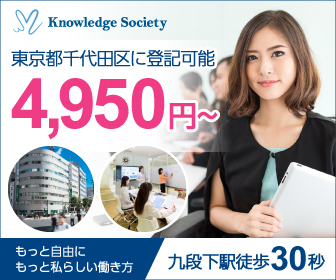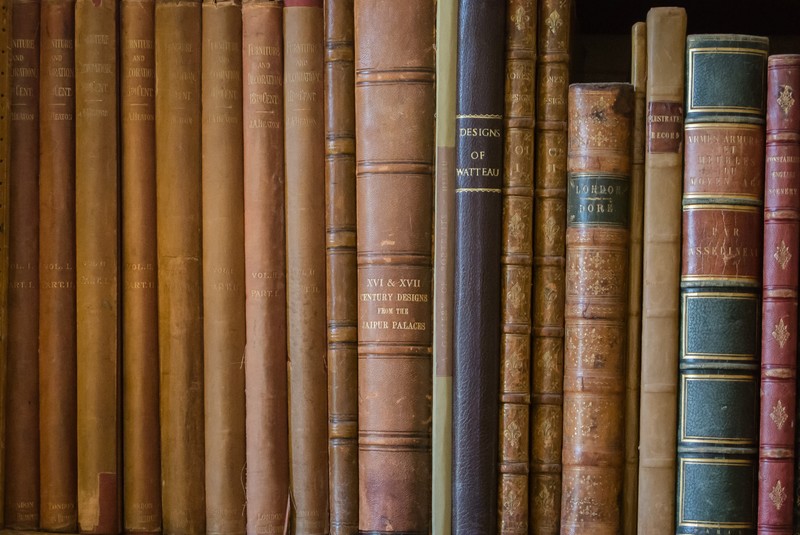内田和成著、「仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法 」を取り上げます。
仮説を立てて検証しながら仕事を進める、というプロセス。コンサルティングの世界だけでなく、どの分野の仕事でも必要なスキルです。
本書を読んで、その意義や目的を再確認してみましょう。
仮説を立てて検証する
なぜ、「仮説を立てて検証する」というプロセスが重要なのか?
それは、闇雲に網羅的に情報を集め、その結果をベースに結論を組み立てる「網羅思考」では、時間がかかりすぎ、効率が悪いからです。
「仮説思考」は、情報が少ない段階で仮説を立てて結論までの道筋を作り、その仮説が成立することを検証していきます。
その仮説に関係のあることにフォーカスして情報を集めることになり、この点については効率があがるということです。
もちろん仮説ですから、正解ではないこともありますが、それは検証する中で早い段階で見えてくることが多く、成立しないことがわかれば別の仮説に切り替えて再度検証していくという流れになります。
「網羅思考」は完璧を期しているつもりでも、途中で間違っていることに気づいた時の後戻りが大きく、時間切れになってしまう可能性もあります。
また、情報が多すぎると、かえって意志決定が遅くなるという面もあります。
著者の経験則では、ということになりますが、「問題解決のスピードが格段に早くなる」(p.22)ということです。もし懐疑的に感じる方がおられれば、このこと自体も仮説と考えて、実践してみましょう。
実験をする前に論文を書く
興味深かったのは、本文p43、「実験をする前に論文を書く」でした。
理系の方にとっては、実験をたくさんやって結果を得て、それをまとめる段階で論文を書く、というのが通常考える順番です。
ですが、アメリカにある大学の免疫学の指導教官は、ある日本の研究員(当時)に、「実験をする前に論文を書け」と指導したのでした。
これがスピードで競争にかつ方法である、と。
この話、まさに仮説思考です。仮説を立てて論文のストーリー全体を書いておき、その仮説を検証するべく、そのストーリに従って実験をしていく。
ビジネスの世界においても、仮説思考を取り入れる動機は同じです。
網羅的に情報を集めてから行動していたのでは遅い。競争に勝てない。
そこで、少ない情報からのスタートでもよいから、仮説をたて、それを検証しながら仕事を進める、ということです。
本書を読んでいただきたい方
コンサルテイングの世界では、入社1年目から「仮説、仮説、仮説」と攻め立てられるようですが、一般的には、会社に入って数年から十数年経った中堅層あたりの方にヒットするように思います。
与えられたタスクをひたすらこなさないといけない時代から少し抜けた頃ですね。
課題が何かを見極め、それを仮説思考によって解決までの道筋を考える。あるいは課題自体を仮説思考で考える。
仮説に沿ったストーリーを明確に示すことができるようになるという点で、具体的なタスクに落としこんで部下を動かすときにも必要なスキルとなります。
繰り返しになりますが、「問題解決のスピードが格段に早くなる」(p.22)という点、もし懐疑的に感じる方がおられれば、このこと自体も仮説と考えて、実践してみてください。