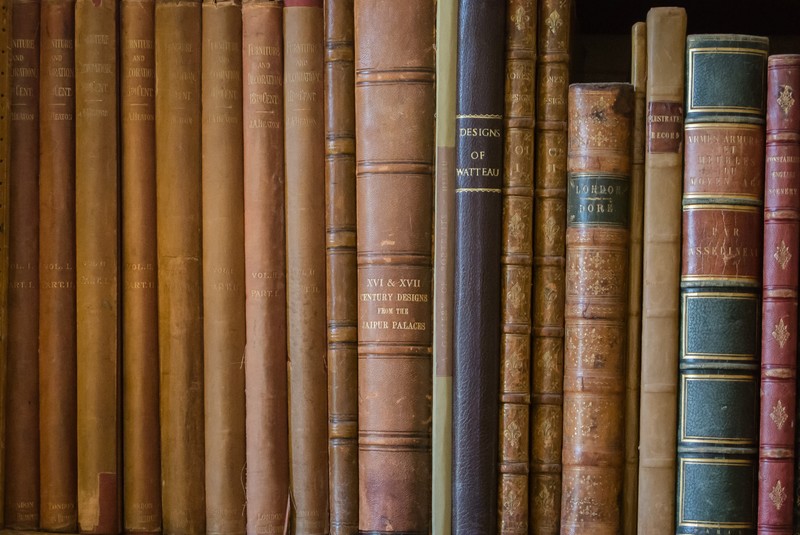桐山岳寛著、「説明がなくても伝わる 図解の教科書」をとりあげます。
仕事で日常的に資料づくりに関わっている方の中には、
「図も説明もしっかり考えて書いているはずなのに、思っているほど他人に伝わらない」
と感じる方も多いかと思います。
そのような人向けに、伝わる資料や伝わる図を作るための考え方やコツについて、
特に”図解”という切り口で書かれた本です。
資料を読む時、人は最初に”図”を見る
仕事で資料を作る人なら、これは少なからず経験があるかと思います。
いろんなキーワードを検討して練りに練った文章でも、実は人はあまり文章を読んでくれないんですよね。
それはなぜか?
やっぱり、他人が書いた文章を読むのって面倒だからです。
自分にとって興味がある人が書いた文章なら、無条件に読んでやろうと思うかもしれない。
でも、そうでなければ、なるべく労力を書けずに資料の内容を簡単に把握したいと思うもの。
仕事ですから。他人の資料を読むのに自分の時間を無駄に使いたくないと考えるのは誰しも当然です。
だから、ダラダラ長い文章は読んでくれないし、図が入っていたらまずその図をみて内容をつかもうとするのです。
伝えたいことを”図”に込める
でも、もしそうなら、逆に図の方に自分の主張を込めればよいのです。
図を見て、これはおもしろそうだと興味を持ってもらえたら、本文の方も目を通してくれやすくなる。
読む人にとって「必要な情報」、「興味深い情報」が、直感的に理解できる図で示されてたら、それだけでまず資料の内容の概略は伝わるし、資料にのせた説明も時間をとって読んでもらえるでしょう。
そう、文章ではなく”図”に説明させるのです。
本書は、図で説明することの重要性、そしてどのように図を工夫すれば相手に伝わりやすくなるかについて、豊富な事例とともに解説されていますが、その図がそもそもなぜ重要かは、概略このような話の流れです。
主題の設定と情報整理
普段から仕事で資料づくりに関わっている方なら実感があると思いますが、図を作る時に、そこに盛り込むたくさんの情報を適切に分類しながら、最終的にその図で伝えたい主題が際立つように図を構成しなければなりません。
この重要性については本書でも指摘されていますし、「主題設定」と「情報分類」とを同時に行いながら、主題が際立つようにするようにと説明されています。
そして、ここがうまくいけば、あとは見せ方や仕上げ方といった、どちらかというとテクニカルな面の問題をクリアすればよく、本書の例を何度も見て実践を積みながら会得することになります。
50の事例集:プレゼン資料、報告資料の読みやすさがアップするヒント集
第4章には、50の事例集が載せられています。
資料作りをするときには、この本を手元に置いておき、リファレンスとして活用するとよいでしょう。
すべての事例が、「失敗例」と「成功例」の対比で説明されています。
両者を見比べることにより、その違いを理解できると思います。
「今まさに、この事例と似た資料を作りたいが、いつも自分の資料はこの失敗例のようなものになる」というものがあればよいですね。成功例がとてもよいヒントになるはずです。
おすすめしたい人
普段、仕事で日常的にプレゼン資料や報告書、マニュアルなどの資料作りに関わっている人にはおすすめです。
一生懸命考えて作っているのに、思っているほど読む人に伝わっていない、と感じている方には、改善策のヒントがたくさんあると思います。
「文章が主で図は添えるもの」、という考え方から、「図こそが主で本質」という考え方に頭が切り替わりますし、仕事で実践をたくさん積めば、自分にあった資料づくりのコツが見えてくると思います。
また、自分の思考を整理するときにも有用だと思います。
自分向けに思考をまとめた資料を作っておくと、数カ月してから読み直すことがあったときに、すっと頭に入るようになっているでしょう。
数カ月もすると、自分が書いた文章はほとんど他人が書いたもののようになってしまいますが、そのときこの”伝える図”が役に立つはずです。